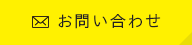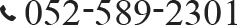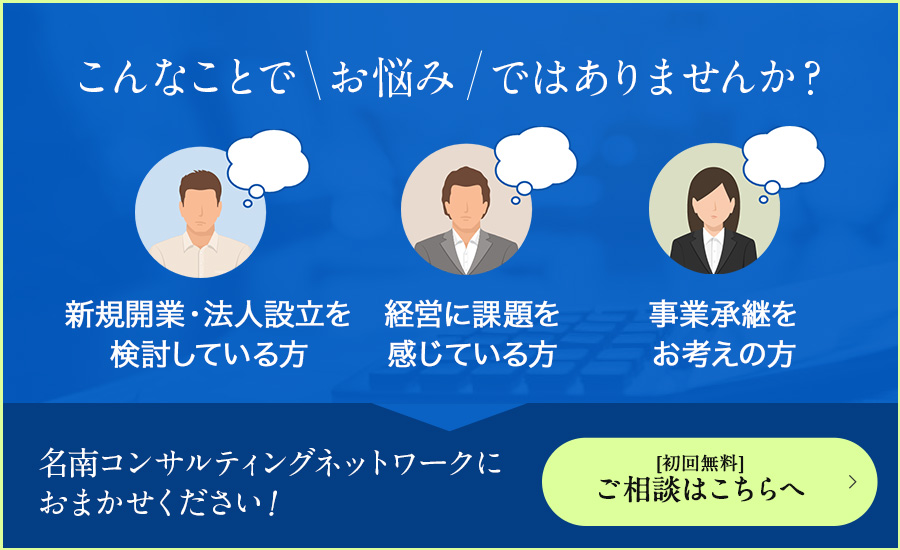暗号資産の動向 2025.10.17
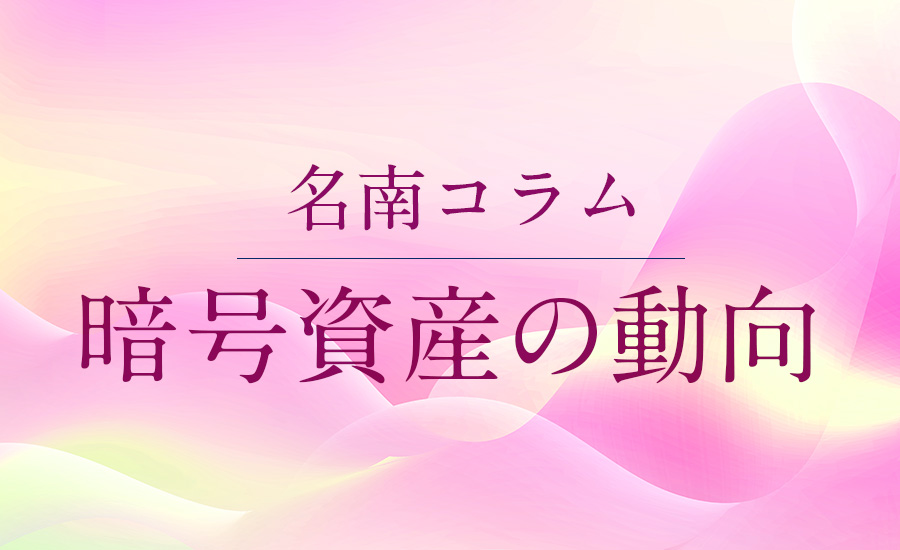
現行の日本の税制において、暗号資産の売却益や交換差益は「雑所得」として課税されます。個人の場合、他の所得と合算されて総合課税されるため、最大で 45%の所得税率と住民税10%が適用されることになります。
法人の場合は法人税の課税対象となります。主な課税対象は以下の通りです。
・暗号資産の売却益(日本円や他の暗号資産との交換)
・マイニング 、ステーキング 、レンディングなどによる暗号資産を取得するような報酬
・暗号資産を用いた商品の購入やサービスの利用時の利益
・暗号資産による寄付を行った場合
※マイニングとは世界各国でなされている暗号資産の取引データを検証・承認して、その報酬として新しい暗号資産を得る行為のこと。
※ステーキングとは自身が保有している暗号資産を預け入れることで、その暗号資産のブロックチェーンネットワークの維持管理に貢献し、その対価としての報酬を受け取る行為のこと。
※レンディングとは自身が保有している暗号資産を貸出して、その対価として利息を得る運用をする行為のこと。
◇暗号資産を単に取得しただけでは課税が生じることはありません。また暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その取得時点では課税対象となる所得は生じていないこととされています。
暗号資産について、税制上主な課題として以下が上げられます。
・所得が多い場合、最高税率が適用されて税負担が大きい
・原則として損益通算・繰越控除ができない(株式・投資信託や FX とは異なる)
・暗号資産同士の交換や少額の決済でも課税が発生して計算が煩雑
・もともと匿名性やディセントラライズドな設計を基に構築されたものである為、全ての事象を税務当局が補足することが難しい。
※ディセントラライズドとは中央集権ではない分散化されたという意味で、基本的に中央政府が管理していないものという意味
今後の暗号資産にかかる税制改正の動向
現行として暗号資産取引は所得税においては雑所得扱いで総合課税となっていますが、今年に入り、業界団体である日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)と日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)などが税制改正要望書を金融庁へ提出しており、また日本ブロックチェーン協会(JBA)も要望書を出していることもあり、金融庁では暗号資産取引について課税制度の見直しを求めて申告分離課税導入への検討がされています。
株式やFXのように分離課税で一律 20%税率とすることにより、税負担の軽減や計算の簡素化が期待されます 。また取引での損失や利益を他の所得と損益通算したり、翌年以降に損失を繰越したりできるようにすることにより、従来の投資商品と同様の扱いとして投資の参入障壁を下げて、国内市場の拡大、活性化を図ることを視野に入れています 。さらに暗号資産での日常的な決済の普及のために一定額以下の決済取引について非課税とする制度の導入も検討されており決済利用手段としてのハードルを下げる考察もあるようです。
法人への課税について、暗号資産は原則期末時価評価課税としており、そのような状況に対して一定期間の保有に対する課税猶予などが検討されています。またスタートアップやWeb3企業の海外流出を防ぐほか、暗号資産の最新の市場規模は 2025 年時点において500兆円規模となっており、金融市場で大きな存在感を持つようになってきています。それにより現状を加味すると国際競争力を維持・高める施策として重視することが求められています。(2025 年 9 月時点で東京証券取引市場全体の時価総額がプライム市場約1075兆円、スタンダート市場約33兆円、グロース市場9兆円の合計1,117兆円であること、また暗号資産は2014年時点で約1兆円規模から2025年の約10年間で500兆円まで大幅拡大しているその成長性も無視できないものとなっている。)
上記を踏まえて、金融庁や国税庁では暗号資産というものをどうとらえているのかという問いでは、「通貨」か「金融商品」なのかという疑問がわいてきます。
現状日本ではどちら側も持ち合わせているという見解となっており、単純にどちらかという分類を示すのは難しいようです 。
資金決済法における通貨としての側面では、物品の購入や役務提供の対価の弁済に使用できる財産的価値と定められており、法定通貨(円やドル等)とは区別しつつ、支払い手段としての機能に注目して通貨に準ずる扱いをしています。これにより暗号資産交換業者は、この法律に基づき顧客資産の分別管理などの厳しい規制を受けて運用されています。
金融商品の側面では、価格変動が大きく、投資や投機目的で取引される現状を踏まえると金融商品としての性質が強いともいえます。またビットコインなどは発行枚数上限が決められている為、価値の保存要素も強くデジタルゴールドとも呼ばれています。そのような性質もあり有価証券や現物資産などの性格も有しているため金融庁では、これまで資金決済手段として定められていた暗号資産を金融商品として法的に位置づける方針であることなども報じられており、金融商品取引法の適用を検討している段階です。
現時点では資金決済法が適用されていますが、金融資産としての性質が非常に強いという側面は無視できないため、両方を合わせ持つハイブリッドな存在として捉えられています。また今後、金融商品取引法での規制が強化される方向で議論が進んでおりその位置づけは今後さらに明確化されていくかと考えられています。
最後に投資対象として暗号資産は現代の一資産として一般に認識されるのかという問いについて、もちろん個人投資家や機関投資家からの関心は集めている現状もありますし、民間企業も投資対象として保有しているケースも出てきています。また政府として準備金目的で保有する事例も出てきていることや、これまでの市場規模の拡大を鑑みると、一つの投資先として考えられる基盤は整いつつあると考えてもいいのではないでしょうか。
また昨年から米国ではビットコインの ETF(上場投資信託)が米国証券取引委員会(SEC)で承認されて取引が開始しており、他の暗号資産通貨も前年後半以降で承認され始めています。まだ日本では暗号資産の価格指数と連動する ETF の承認はされておらず取引はできませんが、いずれ日本でもETFが承認され、暗号資産自体も金融商品と扱われる環境が整備されていくような予想ができる状況となっています。
ただ個人的には暗号資産の値動きは他の資産と比べて非常に価格変動が大きく、比較的新しいものであるため、流動性がまだ低く市場の過剰反応や感情的な取引が激しい価格変動を招く結果となっているように感じます。暗号資産が出始めて 10 年ほど経過して認知はされているが、まだ実際に投資する段階には遠い存在のような印象です。
今後、暗号資産の税制上の取り扱い、投資資産としての側面や決済手段としての利便性など、その改定や動向に注目していきたいと思います。